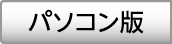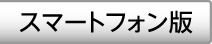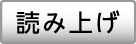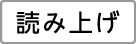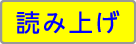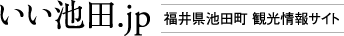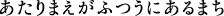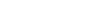水海の田楽能舞(国指定重要無形民俗文化財)※毎年2月15日開催
最終更新日 2026年1月5日
ページID 004054
水海(みずうみ)の田楽能舞
鎌倉時代から伝わるという「水海の田楽能舞」は、この地に受け継がれて約760年。
鎌倉幕府の執権であった北条時頼が諸国行脚の折、雪で立ち往生し、水海で越冬した際に村人たちが「田楽」を舞って慰めたところ、時頼が返礼として「能舞」を教えたのが始まりと伝えられています。
毎年2月15日、ぴんと張りつめた空気の中、古式に従って田楽四番と能楽五番が厳かに奉納されます。観客を幽玄の世界へと誘う、池田町が誇る伝統行事をじっくり堪能してください。
※2026年は通常通り開催を予定しております。
※シャトルバスは運行いたしません。
※見学スペースに限りがあるため、報道関係者以外は三脚、一脚、自撮り棒、脚立のご使用はご遠慮ください。また、演者や他の見学者へのご迷惑になるような行為(フラッシュをたく、長時間視界を妨げるなど)はお控えください。
場所
福井県今立郡池田町水海52-24 鵜甘神社(うかんじんじゃ)
※お車の方は「水海しめ縄会館(福井県今立郡池田町水海54-1-1)」周辺に駐車してください。交通誘導員の指示に従って、円滑な駐車にご協力をお願いいたします。
時間
正午 禊
午後1時から午後5時頃まで 田楽能舞奉納
特徴など
田楽とは、平安時代に庶民が田植えなどの農耕儀礼に笛や拍子をつけたものです。その田楽と貴族のたしなみである能が同時に奉納されるところに特徴があります。
舞人も囃し方も水海地区の住人で、中学生からお年寄りまで、冬の間毎日練習を重ねます。
舞人のうち、「翁(おきな)・祝詞(のっと)」、「三番叟(さんばそう)」、「高砂(たかさご)」の舞人を務める3人の男性は、3日前から他人が作ったものを食べずに身を清める「別火(べっか)」を行い、当日は川でみそぎを行います。
田楽能舞は午後1時から始まり、半日かけて田楽4番、能5番が舞われます。
関連情報
地図
Google Maps サイトに移動して表示する(新しいウインドウが開きます)
カレンダーで探す
2024年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
緑色背景の日が開催日です。
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。